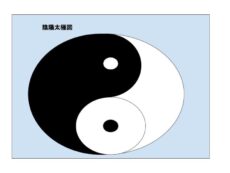- 易って時代劇でよく見る易者の易ですか?
- そんな古いもので何が判るんですか?
易(えき)って時代劇で良く見る、あの易者の”易”ですか?


そうですね、江戸時代の頃、武士が浪人となった時の仕事として盛んだったと聞いています。
武士は、それなりに勉強された人が多く、人によっては中国伝来の四書五経という物まで読破された人もあったようです。その四書五経の中に、春秋、易経,などがあり、易の原本と言われているのが、易経なのです。
江戸時代の浪人の仕事として、提灯や笠の貼付けもありましたが、文武の文に長けている人達は、街角の占い師を選んだのです。
もっとも、占い師とは言わず”八卦観”(はっけみ)と町人の世界では呼ばれていたそうです。

なぁんだ、古い江戸時代の占いなんて、カビ臭いわねえ…!
この占いは、江戸時代より前、平安時代より室町時代より、もっと前から伝わっています。
どこからと言うと、今から5000年前の中国からです。
殷の前の時代、伏犠氏の頃と覚えて下さい。
夏(か)の国とか、○×皇帝の時代とか言われていますが、古代中国の人達からなんだ…と認識するだけで良いです。



そんな化石みたいな占いが、
どうして今まで継続されているのですか?
易経は占いの書物だけではありません、人生を渡る”哲学書”と捉えましょう。
皆さんが、占いをするのも人生を良い方向へと歩きたいからですよね。
どの道を歩くと、こんな具合になり、この道を歩けば、穴ぼこが待っているので、気を付けましょう…! と、
その歩きたい方向の”羅針盤”という物が、易経には書いてあるのです。
占いを使いながら、人生の正しい歩き方も教えてくれるのが易経です。
明治、大正、昭和に平成、そして令和の時代までも易経は語り続かれているのは、
こういう人生哲学から導かれる正しい占いなのだと感心します。
未来永劫続くとされる、この易経は修得せねばなりませんし、人生修行に大きく加算されることでしょう。
そんな古いもので何が判るんですか?
占いは命卜相と言われる分野があり、
命は四柱推命、紫微斗数推命など文字通り、運命とか宿命を推命します。
相は手相、人相,顔相などの観相学が該当します。
卜の占いは、吉か凶の判断を求められるので、この易経が該当します。
最近は、タロット占いなどもあり、数秘術、マヤ暦など様々です。
しかし、この易経での占い方法の、やり方が誤解を生む元となっているのは否めません。


<ある投稿の例文>
この八卦を算出するのに、
筮竹という竹とか、
サイコロを使います。
人の人生を模索するのに、
束ねた竹とか、
サイコロで決めるなんて、
不謹慎極まるものだ…と思います。



私もこういう経験がありました。
どんな占いの占術を使っても、占い師として、決断とか占断を迫られる時があります。八卦では、不合格となっているが、何とか合格させたいと思った時、占いの神様に問いかけたくなります。それでも、この易経の八卦が教えるのは、初筮は告ぐ…です。
占い師も判断に迷う事もあります。苦しい時や、困った時に、神様にすがるのは皆さん一緒です。占い師が神様にすがるのは、<易の神様>、ただ一つです。
易で占うのは、あなた自身、易の占断を決めるのは、易の神様だけ、易の神様が形として現れているのが八卦なのです。
この八卦の中には、優しさも強さも厳しさも含まれています。
占い師の感情は一切含まれてはいません。
それだけに、占断の目的を確実にすることが必要となり、占的を如何に絞り取れるかが占い師の力量となります。
<サイコロだとか、竹のひごで何が判るか?> と豪語していた自分が恥ずかしくなりました。あの中には神様からのお告げが隠されていたのですね。
八卦の図形を読み解き、解釈そして納得する事が、神からのお告げ、メッセージとしてとらえることが出来るのは、易経以外にはありえないと思った次第です。
先人が学んだ易経を、これから勉強していきたいと思いますが、易経だけに捉われず、九星気学、宿曜経、算命学などとも連携して肉付きの良い易経としてブログに掲載したいと思います。



最後まで読んで頂きありがとうございました。